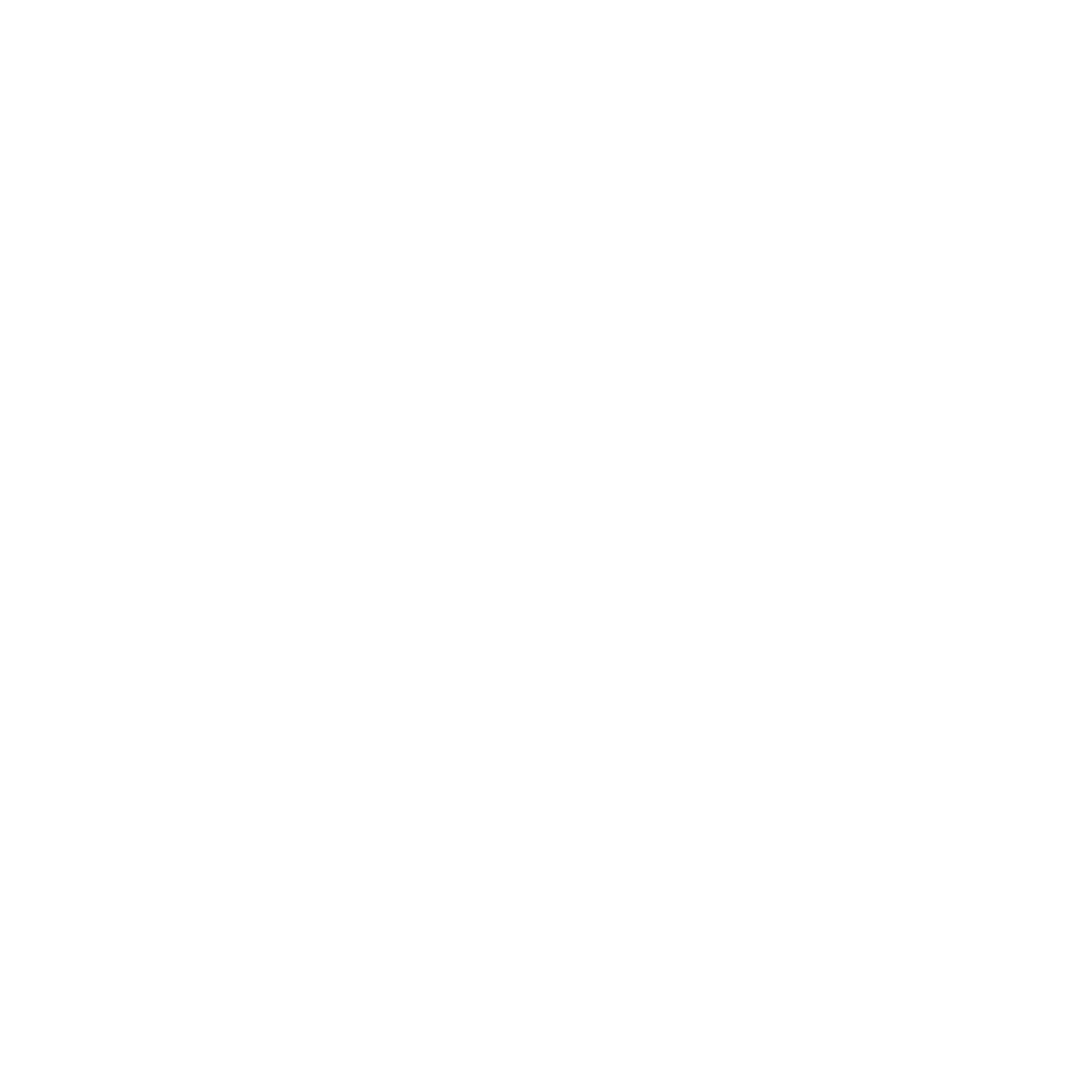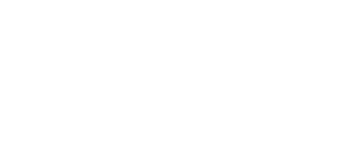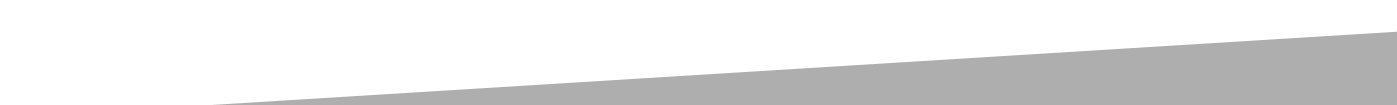受け継がれる想い
伊藤正次から受け継がれる想い。想いをひも解くインタビュー。
Vol.1
演じるのではなく、存在すること。
俳優
斎藤 工
Saitoh Takumi
歌いたい、と思った。
2011年3月11日。東日本大震災が発生。俳優として、自分にできることが限られていることが本当に歯がゆかった。そして、同時に「先生が生きておられたら、この状況でどうされていただろう」と、考えずにはいられなかった。
先生なら、絶対に被災地に自分の足で入り、自分で見て感じて、そこから何か行動しただろう。そう考えたら「歌う」というライブな表現で、その場所に存在することも役者の自分にとって自然なことに思えた。その思いが、シングル「燦々」のリリースへとつながる。
俳優が歌を出す。そのことで、少なからず誤解を受けることも覚悟した。けれども、歌うということは、その楽曲の世界の中に自分が「存在」しているということ。それは、俳優として「役を生きる」ことと本質的に同じ。そう考えたからこそ、本気で歌いたかったのだ。
「でも、もし自分が研究所に行っていなかったら、俳優でありつつ音楽の力でも何かしようとは思わなかったはず」
明日に逃げず、今から目をそらすな
いま、自分の周りで起こっていることのすべてに当事者意識を持て、というのが伊藤正次の教え。俳優、斎藤工が「親以上に、親だった」と語る、師の教えは、いまもどんなときも自分の行動の基本となっている。
そして、師の言葉を思い起こすとき、決まって居住まいを正さずにはいられなくなる。まるで、その場で伊藤正次と向き合っているように。
「明日に逃げるな。今日、どれだけの熱意で生きられるのか。その言葉がずっと、自分の中に残っているんですね。それは、なんていうか木の幹みたいに、しっかりと残ってる」。研究所に入って、最初の授業で出された問いが「デモクラシーとは何か?」というものだった。その問いは俳優、斎藤工としての幹を形成する年輪の中心に刻まれている。
「もっと、滑舌だとか、そういうことを指導されると思っていたんです。ところが、全然。世の中で起こっていることの本質だったり、歴史や演劇そのものの意味だったり。とにかく、そういった深いことに触れさせてもらったのが研究所での先生の授業だったんです」
その当時、授業でとったノートは数十冊にも及ぶ。そして、今でも、ノートを読み返す。
「先生から離れたあとも、ノートを開くと、いま、自分に必要なものが飛び込んでくるんですよ。それが、あまりにも多い。先生は、人生には“まさか”がたくさん起こる。それをどう乗り越えるか。唯一、そこで人間は進化するんだと言われて。先生の話は、とにかく引き込まれるんです。先生の、ものすごい体験を含めて、すべてが自分に迫ってくる感覚」
その授業は、毎回が、一度限りのライブ。絶対に見逃したくなかったという。
軽く、何かこなすことの怖さ
まるで「生きるということは、こういうことだ」というのを身を削り、身をもって教えられるような研究所での時間。その姿勢は自ずと、芝居という舞台の上でも表れてくる。
「研究所の公演で、裏方として車夫の声だけをやったんですね。裏方なので黒子の格好で。そうしたら、先生が車夫の饅頭笠を持ってこられて、これをちゃんと着ろと。登場していなくても、完璧にその衣装をまといなさいと叱られて」
演目が終わったあと、舞台挨拶で観客は、舞台に登場していない人物までもが、みんな本物の衣装を着ていたことに驚き、斎藤自身も身震いした。
「見えている、見えていないは関係ない。いつも本物でいることが大切なんだと。先生が追求しておられたことは、今でも自分の基準になっています。逆に、軽く何かをこなしてしまうことが本当に怖い。先生がおられたら、張り倒されるなと(笑)」
表現の世界、メディアの世界でも効率と数字に追われがちな現実があるからこそ、余計にそう感じる。
「でも、それを言い訳にはできないし、したくない。どんな状況でも準備不足で人前に出て、それが残ることが一番怖い。だから、限られた時間でもやれることはやらないと」
境界線のない生き方
研究所で斎藤は、演技技術そのものを教えられたことは、殆どなかったという。それよりも、もっと大切なものを発見する。
「演じるというのは、憑依するとか、まとうとかではなく、存在することなんだと。誰かの、ほんの一部分を演じることであっても、ただ演じるのではなく、そこに存在していなければならない。そのために、演じるその瞬間の前後、奥行き、背景、どれもが俳優には備わってなければできない仕事なんだと学びました」
演じるというのは、ときとして、その演技の持つ何かに流されてしまうこともある。だからこそ、演技に自分が流されないようにすることの大切さを師から学んだ。
「俳優は世の中を知るということが、何より大事。そのために自分のアンテナに引っかかってくるものは、そのまま受け取らず、自分で咀嚼して自分の言葉で話せるようにする。それも先生から教わった大切なことです。外国の俳優を見ていて思うのですが、彼らは演じるという仕事を通して、世の中の深い部分とコミットしているように感じるんです。俳優であるということと、ひとりの人間であるというところに境界線がない」
そこを切り離したほうが、楽なのかもしれない。演技は演技、自分は自分だと。しかし、それでは、どちらかがどちらかに嘘をついていることになる。それは結果的に演技を底の浅いものにしてしまう。
一生、勘違いすることはない
「研究所で先生に学ぶまでは、演技というのは技術で上達するのだと思ってました。でも、そうじゃない。存在の深さが、大切なんです。それは何か特別な技術が必要なことではなく、日々を自分というものをきちんと持って生きることで深まる」
そして、とにかく常に本物を見ろ、本物に触れろ、と叩き込まれた。
「伊藤先生自身もそうですが、よく授業でもお話をしていただいた彫刻家の佐藤忠良先生をはじめ、先生の周りにいるさまざまな分野の方々も、本物でした。本物というのは、誤魔化しが効かないところで常に勝負をしている。そういう本物の方が作られた本物の作品を見ていると、自分のやるべきことが山積みなのが分かるんですよ」
本物の持つ、本物のちからを自分の基準に持つ。そこから、自分に足りないものを探すことは今も「クセ」のようになっているという。
遠回りといえば、遠回り。けれども、そこに時間を費やすことを斎藤は「救い」だと断言する。
「自分で自分に時間をかけていることは、本当に大切。この職業で、簡単に何かがうまくいくようなことはないんです。だから、一生勘違いすることはないと思う」
そのまなざしの先には、いつでも斎藤に語りかける師の姿がある。
「いいか、登山と同じなんだ。上にはいくらでも休まず登りつづけてる人がいる。だから、休めないんだ」
斎藤工 Saitoh Takumi
伊藤正次演劇研究所元研究生。映画『時の香り~リメンバー・ミー』(2001年公開)でデビュー。映画『春琴抄』(2008年公開)『SPACE BATTLESHIP ヤマト』(2010年公開)『逆転裁判』(2012年公開)ドラマ『オトコマエ! 』『ハガネの女 Season2』『最上の命医』『大河ドラマ 江~姫たちの戦国~』『QP』など出演多数。舞台、ラジオパーソナリティ、歌手としての活動のほか演劇ユニット『乱―Run―』を結成するなど幅広い分野で活躍。
斎藤工 オフィシャルサイト

斎藤工さんが出演された下記の番組内で当研究所が取り上げられました。
* NHK『スタジオパークからこんにちは』 2012年6月1日放送
* NHK『ミュージック・ポートレイト』 2013年5月16日・23日放送